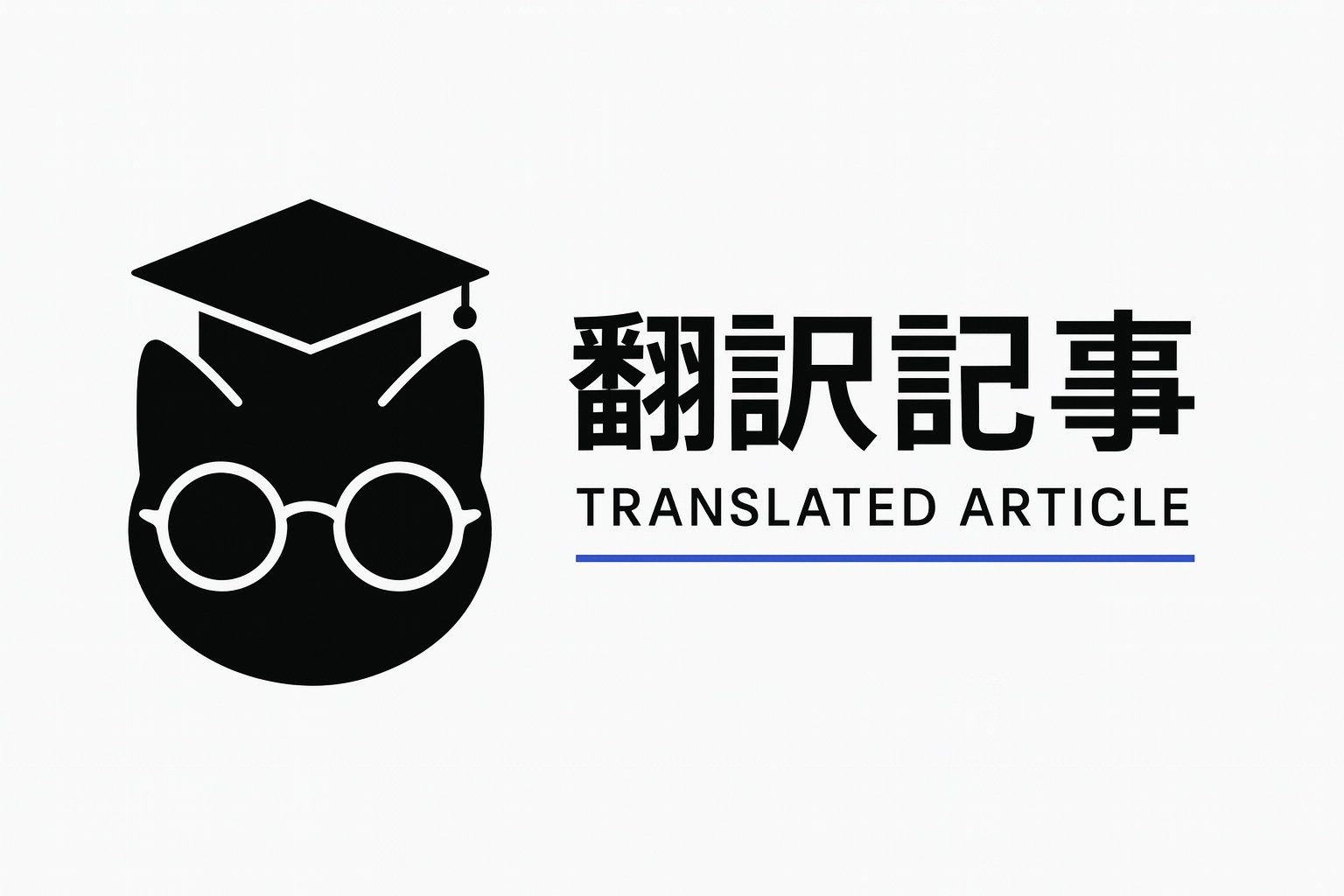オーディオ用の専用AC電源ラインと屋内電源改善について
– 2024年8月更新 –
著者:ヴィンス・ガルボ
この記事は、MSB Technology社のヴィンス・ガルボ氏が公式フォーラムに投稿した英語版ドキュメント「Dedicated AC power lines and wall power improvements for audio」を日本語に翻訳したものです。元記事は20年以上の実績に基づく専門的な技術文書であり、オーディオ愛好家にとって非常に有用な情報を含んでいます。
免責事項
この文書の内容は、潜在的に致命的な高電圧に関わる作業を含みます!!ここで述べる推奨事項を最後まで読み、電気工事士に内容を渡して作業を任せてください。Galbo Design、Vincent Galbo、および MSB Technology Corp. は、本書に記載された手順に従った結果生じるいかなる負傷や損害に対しても保証も責任も負いません。 情報が正確か完全かについても保証はありません。本書はあくまでも個人的な助言として無償で提供されているものです。安全に解釈・施工するためには、必ず資格を持つ専門家のサービスに依存してください。この文書の読者は、誰が作業を行う資格があるかを判断する責任があります。また、ここでの推奨事項が地域の建築基準や法令に違反しないかを確認する責任もあります。本書の内容を実行することにより、読者および電気工事士は全ての責任を受け入れ、Galbo Design、Vincent Galbo、および MSB Technology Corp. を免責することに同意したものとみなします。
私たちがここで達成しようとしていることは何か?
ここで繰り返し強調します!!賢明に考え、この文書を有資格の電気工事士に渡して作業を任せてください。本書に記載された内容は20年以上にわたって試験され、明確で大きな聴感上の改善が確認されています。これを実施した人々からは「音が良くなった」程度の反応ではなく、ほとんどの場合「これはずっと求めていた音だ!なぜ誰も話題にしないのか?」という驚きの声が聞かれます。ここでの主な目標は、オーディオシステムに供給する壁内配線を太くすることです。
読み進める前に
多くの人は「20アンペアの専用回路がある」と言い、それで十分だと考えています。しかし米国の電気規格で「20アンペア専用回路」と言えば、壁内の配線は12ゲージ(3.5sq)です。12ゲージ(3.5sq)の配線はハイエンドオーディオシステムには絶対に不足しています。本書では10ゲージ(5.5sq)またはそれより太いワイヤを推奨します。ゲージは線材の太さを表すアメリカンワイヤゲージ(AWG)で、数値が小さいほど断面積が大きくなります。ここで重要なのは「専用回路」であることよりも配線の太さ(ゲージ) です。
注: 本文に出てくるAWG(アメリカンワイヤゲージ)と日本で一般的な「スケア(sq)」の換算は以下の通りです。10 ゲージ=5.5 sq(5.261mm²)、8 ゲージ=8 sq(8.368mm²)、6 ゲージ=14 sq、2 ゲージ=38 sq(33.63mm²)、1 ゲージ=38 sq(42.41mm²)、2/0 ゲージ(2オット)=60 sq(67.42mm²)。日本の電線規格はスケア(sq)で表記するので、配線を選ぶ際の参考にしてください。
本書では、アンプの大きな内部電源が音楽信号に応じて大きく電流を要求する際、その電流変動が配線抵抗によって壁からの電源ラインを変調(モジュレーション)してしまうという理論に基づいています。壁コンセントから分電盤まで10〜15フィート(約3〜4.5 m)の距離でも、12ゲージ(3.5sq)または14ゲージ(2sq)の配線では抵抗が大きすぎます。電力会社から供給される電源ノイズは思っているほど大きくないことが多く、むしろ配線の太さが非常に重要です。アンプは60 Hzの商用電源よりも高く、また低い周波数で瞬間的に電流を要求し、これがライン電圧を揺らして自身の出すノイズを再び電源から取り込む原因となり、プリアンプやDAC、サーバーなどにも悪影響を与えます。壁配線の抵抗が長さやゲージによって決まり、アンプが電源を変調する度合いが決まります。電源コンディショナーや特定の電源ケーブルはこのノイズをシャント(短絡)させ熱に変えて減衰させますが、12ゲージ(3.5sq)では音楽に合わせた瞬間的な電流供給が十分でないため、ダイナミクスの低下や中高域のぼやけ・細部の欠落が起こります。
より良い解決策は、ブレーカーパネルまでの抵抗を小さくすることです。それによってアンプが電源ラインを変調しにくくなり、同時に音楽再生時に瞬間的に必要な電流を十分に供給できるようになります。つまり抵抗を下げることで二つの利点があります。(1) アンプが屋内電源を変調するのを抑え、(2) アンプの電源供給を最大化して驚くほどの明瞭さを得られることです。本書の最大の目標は、配線の抵抗を下げるために、20〜30フィート(約6〜9 m)までは10ゲージ(5.5 sq)、35〜40フィート(約10〜12 m)では8ゲージ(8 sq)、60フィート(約18 m)を超える場合は6ゲージ(約14 sq)の配線を採用することです。 この他の手順は、太くした配線の性能を最大限に引き出すためのものですので、どの工程も省略しないことが重要です。
導電性接続用ペースト
MG Chemicals – Silver Grease 8463A → こちら
Amazonで購入 → こちら
これらのペーストは「グリース」と呼ばれていますが、かなり粘度が高いものです。市販されている中には液体状で、電圧差によってラインとニュートラル間を移動し、ホットとグラウンドを短絡させてしまう報告があるものもあります。MG Chemicals製は最も粘度が高く、極間の距離が1.5インチ(約3.8 cm)以上あれば移動しにくいとされています。また酸化もしにくいようです。オーディオ用に販売されている銀ペーストには酸化しやすいものもあり、酸化した銀は塗らないほうがマシという結果になることもあります。
電源コード製作時にプラグ端子にこのペーストを塗ることは避けてください。電圧差によりペーストが移動しやすく、端子間が近いためショートの危険があります。壁コンセントの両極のように1.5インチ以上離れている場合は使用してもよいかもしれませんが自己責任で行ってください。この銀ペーストは分電盤でブレーカーと配線の接続部分には使用できますが、インターコネクトやスピーカーケーブル、その他の信号用ケーブルには絶対に使わないでください。ペーストは乾燥せず拭き取りにくいため、信号ホットとグラウンドを部分的または完全に短絡させてしまう恐れがあります。実際にインターコネクトに使用して音が出なくなり、端子の洗浄に苦労した事例も報告されています。信号用ケーブルは年に1~2回清掃する(非常に推奨)方が安全です。
インターコネクトやXLR端子の清掃方法やCaig製品などの除酸化剤については、メーカーの指示を参考にしてください。
AC電源に戻ります。
銀ペーストはAC電源のすべての接続部に使用します。まずブレーカーを外し、裏側のクリップの内側に塗布します。バスバー側の接続には塗る必要はなく、バスバーは常に通電しており感電の危険があるため触れないでください。 クリップに塗ることでバスバーへペーストが転写されます。ブレーカーが一年以上経過している場合は新品に交換することを推奨します(オーディオ機器に比べれば安価です)。電気資材店で純正品のブレーカー(Square D、Siemensなど)を購入すると、内部の接点に銀・タングステンが使われていることがあります。ホームセンターで売っている安価な海外製ブレーカーは銅接点であることが多く、抵抗が高く、酸化により抵抗がさらに増え、本書の目的に反します。ご自宅のブレーカーパネルの型番を調べ、電気資材店で接点材料が銀または銀タングステンであることを確認してください。さらに、ブレーカーや壁コンセントで配線をネジ止めする部分にも銀ペーストを薄く塗布します。塗り過ぎは逆効果です。ペーストは手や工具に付きやすいため、作業後はGoo Goneのような溶剤で見える部分も見えない部分も入念に清掃してください。ご使用の電気工事士は酸化防止のペーストを持っているかもしれませんが、それは接続部の酸化を遅らせるだけで抵抗を下げる効果はありません。本書の目的には適さないので、電気工事士のペーストは使用しないでください。 銀または銀メッキされた銅を用いたペーストのみが対象です。
20 アンペア/120 ボルト回路を最低2本、10ゲージ(5.5 sq)配線で20~25フィート(約6~8 m)まで、8ゲージ(8 sq)配線で40フィート(約12 m)まで、6ゲージ(約14 sq)配線で75~80フィート(約23~24 m)まで引き回すことを推奨します。8 ゲージを使用する場合は、標準的な壁コンセントには10 ゲージまでしか接続できないため、コンセントの近くで8 ゲージから10 ゲージへのジャンパーボックス(接続箱)でつなぎ替える必要があります。Furutech製の8 ゲージ対応コンセントもあると聞いており、8 ゲージを使う場合はそれを採用すると良いかもしれません。6 ゲージでは必ず接続箱を通じて10 ゲージに落とす必要があります。この接続部には銀ペーストを使用し、接続点の抵抗が配線よりも低く、長期間維持されるようにしてください。ブレーカーは20 アンペアを推奨します。30 アンペアブレーカーは通電時の抵抗が低いわけではなく、遮断値が30 アンペアに設定されているだけです。過負荷や短絡の際に遮断する安全装置としては20 アンペアで十分ですし、30 アンペアだと短絡時に火災を招く恐れがあります。
プリアンプやDACなどフロントエンド機器には1本、各パワーアンプにはそれぞれ1本、サブウーファーがあれば1本(または2台で1本)の専用回路を設置してください(サブウーファーはアンプ以上にラインを汚染します)。PS Audio Power PortやFurutech、Wattgateなどの高品質なコンセントを使いましょう。業務用の安価なコンセントは代用品にはなりません。中価格帯のオーディオ用コンセントは、厚い銅材料や良質なメッキ、プラグ刃の掴みが強いため投資に値します。
サブパネル(分電盤)
壁コンセントから分電盤までの距離が60〜75フィート(約18〜23 m)と長い場合は、リスニングルーム近くにサブパネルを設置することを検討してください。距離が80〜150フィート(約24〜45 m)になる場合はサブパネルは必須です。EatonのCHシリーズなど、バスバーが銅製で銀メッキされたサブパネルを推奨します。内部の電源経路が高導電率で、抵抗が小さいからです。本書の目的に従い、メインパネルとサブパネル間の配線ゲージを太くするよう電気工事士に依頼してください。最低でも2 ゲージ(約38 sq)を、距離が80フィート(約24 m)を超える場合は1 ゲージ(約38 sq)や2/0 ゲージ(60 sq)を検討します。ここでも重要なのは高電流ではなく低抵抗であると電気工事士に理解してもらうことです。機器の性能が向上するのは、可能な限り抵抗が低い経路を確保することによるのです。
アース(接地)
メインのブレーカーパネルまで6〜10フィート(約2〜3 m)間隔で地面に2本または3本の接地棒を打ち込み、相互に接続しておくことも検討してください。可能であれば湿った土壌部分に設置すると効果的です。最近の建築基準では、住宅の接地を基礎の鉄筋や床の鉄筋に結びつけることもあります。地域の事情に詳しい電気工事士に最適な方法を相談しましょう。
注: 日本では通常 「D種接地工事」 が該当します。接地抵抗値などの規定があり、これも有資格者による施工が必要です。
120 ボルト回路を使用する場合:既存および新設の回路はすべて同じ電源相(フェーズ)に接続することを確認してください。異なるフェーズに接続されたオーディオシステムでは、家庭の両相がアンテナのように働き、高周波ノイズを拾いやすくなります。同じ相に接続することでRFノイズによる機器の損傷を避けられます。通常、分電盤では左側の縦列において上から1番目のブレーカーがA相、2番目がB相、3番目が再びA相…という具合に交互になっています。そのため、複数の専用回路を設ける場合は一つおきに配置することで同じ相に揃えることができます。別の説明をすると、左列の奇数番目は片方の相、偶数番目はもう片方の相に接続されます。右列ではその逆になる場合もあります。新しいパネルでは片側全てが同じ相にまとめられていることもあるので、自分で判断できない場合は電気工事士に確認してもらってください。
注: これは米国の単相3線式240V配電を前提とした記述です。日本の一般的な単相3線式100V/200V配電でも同様の考え方が適用できます。分電盤で2つの異なる100V系統(赤線と黒線など)にオーディオ機器がまたがらないように、同じ系統から電源を取るように電気工事業者に依頼してください。
自身でACテスターを使用して2つの壁コンセントが同じフェーズかを確認することもできますが、この作業は感電の危険があります。テスターに習熟していない場合は電気工事士に依頼してください。同じフェーズであればそれぞれのコンセントの短いスロット(ホット側)同士の電圧はほぼ0 ボルト(数ミリボルト程度)になります。延長コードなどでテスターのリードが届くようにして測定します。長いスロットはニュートラル、短いスロットはホットです。もし2つの短いスロット間で220〜240 ボルトの電圧が測定された場合、2つのコンセントは異なるフェーズにあり、ブレーカーの位置を変更して修正する必要があります。この手順を自分で行うかどうかは自分の技量次第であり、危険性を理解した上で行ってください。自信がない場合は専門の電気工事士に依頼するのが安全です。
注: 日本の場合、異なる100V系統のホット側(非接地側)間で電圧を測定すると200Vが計測されます。同じ系統であれば電圧はほぼ0Vになります。
また、作業終了後に電気工事士にブレーカーパネル内のクランプネジを一通り締め直してもらうと良いでしょう。特にパネルに供給する太いケーブル(アルミ線)部分は大きなネジが使われており、ネジを少し締めるだけでも接触が改善します。これらのネジや端子は常に通電しており、絶対に素人が触れてはいけません。 工具も電圧耐性のある絶縁工具が必要です。この作業を行うかどうか、どのように行うかは電気工事士の判断と責任に委ねてください。
電源のノイズ測定にはGreenwave製のメーター(約135ドル)を使用しています。過去にはAlpha Labsのメーターを推奨していましたが、スケールが変更されて感度が低くなり本書の用途には適さなくなりました。電源ノイズは携帯電話基地局やテレビ・ラジオ送信所などに影響され地域によって大きく異なります。ノイズは導体を通じてだけでなく配線の外側をアンテナのように伝搬することもあります。測定せずにノイズの有無を判断することはできません。メーターの読み取りは日中や夜間など複数の時間帯で行ってください。特に夜に音が変わると感じる場合は測定が有用です。測定はシステムのコンセントに何も接続せずに行います。機器が接続されているとノイズが低下してしまい、測定の意味がありません。ノイズはミリボルト(mV)単位で表示され、50〜100 mVが低レベル、400〜500 mVが高レベル、1000〜2000 mVが非常に高レベルです。重要なのはメーターよりも自分の耳であり、50 mVと40 mVの差のような小さな変化を追いかけるより、より大きな変化に注目してください。一部の電源コンディショナーではメーターとの相互作用でノイズが高く表示されることがありますが、そのこと自体が問題であるとは限りません。コンディショナーを使用した場合と使用しない場合で音を聴き比べて判断してください。
多くの場合、アンプには電源コンディショナーを使用しないほうが良い結果になります。コンディショナーは直列に何らかの処理素子が入るため、アンプに必要な電流供給を制限する場合があるからです。「電流やワット数に制限がない」と明記された製品は内部に並列フィルターがあるだけで電流制限が少ない可能性がありますが、これは相対的な表現であり、小さな制限があることも考えられます。ここでも耳で判断することをお勧めします。フロントエンド機器に関してはコンディショナーを使用した方が良い結果になることが多いですが、電流制限に注意が必要です。1本の回線しか使えない場合は、アンプを直接壁コンセントに接続し、フロントエンドはコンディショナー経由にします。ただし、2本以上の回線を用意し、同じフェーズに揃えることが望ましいです。アンプは音楽の要求に応じて電源を揺らし、静かなラインをも汚染するため、アンプ専用の回線に直接接続し、フロントエンド用には別の回線にコンディショナーを挟むと良い結果が得られます。AudioquestのNiagara 5000などを例に挙げていますが、これに限らず複数の製品を比較してみてください。私たちの経験では、DACを「ハイカレント」端子に接続することで、過渡電流供給とノイズ除去のバランスが良くなることが多いと感じました。他の端子は電流供給を制限しすぎて音が精彩を欠く場合がありました。アンプは壁に直結し、フロントエンドはコンディショナーへという使い分けが基本です。総じて、購入前に試聴できるのであれば試聴し、耳で決めることが重要です。DACやデジタル機器は極めて精度の高いクロックを搭載しており、電源の悪影響でクロックジッターやアナログ回路へのグランドノイズが増えるため、特に適切な電源処理が求められます。
一部のハイエンドアンプは内部配線を変更することで240 ボルト動作に切り替えることが可能であり、その場合は推奨します。どうしても壁配線を太くできない場合や、アンプが対応している場合は既存の配線を240 ボルト用に変更できるか電気工事士に相談してください。アンプ内部のトランス一次側とコアは240 ボルト動作の方が効率が高く、内部電源のインピーダンスが低下する場合があります。また240 ボルトは120 ボルトの2倍の電圧で電流は半分になるため、壁配線から見ると配線が2倍太くなったのと同じ効果があります(オームの法則)。これによりアンプが出すノイズがさらに減少します。ただし、240 ボルト用のコンセント(定格15 A)とプラグを使用し、配線は10 ゲージ(5.5 sq)を60 フィート(約18 m)まで、8 ゲージ(8 sq)をそれ以上に使用してください。必ずアンプ本体の電圧切替機能があり、正しく切り替えられることを確認します。
注: 日本では200Vに相当します。お使いのアンプが200Vに対応しているか、また、200Vへの変更が可能かを電気工事業者に確認してください。200Vで駆動すると、同じ電力を送るのに必要な電流が半分になるため、配線抵抗による電圧降下の影響を半減させる効果が期待できます。
240 ボルトライン用のコンセントには、一般的なEdisonタイプと同サイズで、広い刃が反対側に付いたNEMA規格のコンセントとプラグがあります。HubbellやLevitonの商業用製品で、家庭にも違和感なく使える6-20シリーズのNEMA 6-20P(プラグ)とNEMA 6-20Rまたは6-15/20R(レセプタクル) が該当します。stayonline.comやstore.hubbell.comなどで入手できますが、電気工事士が既に仕入れ先を持っている場合もあります。240 ボルトで使用する場合はアンプを内部で必ず切り替えてください。
注: NEMA規格は米国のプラグ/コンセント規格です。日本では使用できません。200V用のコンセントは、100V用と形状が異なり誤挿入できないようになっているため、日本の規格に合ったものを使用する必要があります。
配線を撚ることについて
住宅用のケーブル(ロメックス)や単芯線を撚ることで、高周波ノイズのほとんどを打ち消すことができます。テレビやラジオの送信所、携帯電話の基地局、マイクロ波中継などから発せられる電界によって誘導されるノイズや、近くのAC配線からの低周波ノイズも抑制できます。一方、撚られた配線は自身から電磁場を放射したり、近くの配線に誘導を与えたりしにくくなります。電気工事士にはロメックスケーブルを6〜12インチ(約15〜30 cm)ごとに1回撚るよう依頼してください。配線の長さを引き延ばし、両端をほうきの柄などに固定して撚ると良いでしょう。筆者はドリルに取り付けて撚りをかけたこともあります。撚りのピッチは均一でなくても良く、その方が広い周波数帯域のノイズを減衰できます。複数の回路を並行して走らせる場合は、それぞれの回線を別々に撚り、撚りのピッチも6〜7インチ(約15〜18 cm)、10〜12インチ(約25〜30 cm)、8〜9インチ(約20〜23 cm)のように変えてください。これにより相互の結合が抑えられます。配線同士は最低でも4インチ(約10 cm)離して敷設し、直角に交差させるのは問題ありません。もし単芯線を電線管(コンジット)に通す場合は、その回路のホット(黒)とニュートラルを撚ります。複数の回路を同じ電線管に通しても構いませんが、金属製コンジットへの誘導を避けるため、PVC製コンジットを使用できるのであればそちらを選びます。機械的なアース線(緑の軽めの絶縁線)は撚らず、コンジット内にゆったりと這わせます。
最近、撚り有り配線と撚り無し配線を比較した2人の顧客は、同じ電気工事士に依頼しましたが、電気工事士が撚りを入れなかったため施工し直してもらいました。2人とも音の違いに驚き、撚りの重要性を実感しました。テレビやラジオ、マイクロ波、5G携帯基地局が至る所にある現代では、これらの電界が機器に与える影響は非常に大きいのです。特にDACの高精度クロックのように敏感な部品だけでなく、全ての機器や信号経路、グランド線にも影響します。
もし電気工事士が本書の内容に疑問を抱く場合、彼らは常に「連続的な電流負荷」を基準に設計しており、各相に負荷を分散させることを考えています。本書の目的は、音楽のごく短いピーク電流に備えて壁から分電盤までの抵抗を極限まで低くすることです。連続的な消費電流は4〜10 アンペア程度で電気工事士の想定より少なく、大きな配線を使うことで電流が増えるわけではありません。まとめると、電気工事士には音楽再生時に瞬間的に発生する極めて短い電流ピークに対応するため、壁コンセントからブレーカーパネルまでの抵抗を可能な限り低くしたいのだと説明すると理解されやすいでしょう。これらのピーク電流は従来の電流計では測定できないほど短時間であり、20 アンペアのブレーカーの定格を一時的に超えることもありますが、時間が極めて短いためブレーカーが動作することはありません。
本書の目的と記述の考え方は次の通りです:私たちの趣味における目標は、システムのボトルネック(チョークポイント)を特定し、それをアップグレードすることです。電源はシステムの最初のボトルネックとなり得ます。システムは与えられた電源より良い音にはなりません。ここで考えるべきことは2点です。(1) アンプによる瞬間的な電流要求とそれに伴う電源ラインの変調やノイズを防ぐため、配線の断面積を増やすこと。(2) 電力会社からのノイズや空中を飛び交うRFノイズを配線の撚りなどで抑制すること。適切に設計された電源コンディショナーはほとんどの場合有効ですが、アンプを「飢えさせない」ことが重要です。アンプが飢えることで発生するノイズは、電力会社からのノイズよりも大きく、測定可能で聴感上も悪影響を及ぼすことがあります。
既存の壁配線の酸化やブレーカーの老朽化、特に配線の長さとゲージにより、本書で提案する電源改造は大半のコンポーネントの買い替えよりも大きな改善をもたらすことが多いです。大出力のソリッドステートアンプで分電盤までが長い場合は特に顕著ですが、真空管ユーザーからも大きな改善の報告があります。
20年以上にわたってこの重ゲージ配線と屋内電源の改善を行った人からは、例外なくダイナミクスの向上と同時に音の細部がより鮮明で、背景が暗くなり音楽だけが浮かび上がると報告されています。初めてこの改造を行った際、筆者は低域とダイナミクスが向上することは予想していましたが、中域と高域がここまでクリアで一体感が増すとは思っていませんでした。その改善はまさに優れたコンポーネントを導入したかのようであり、その明瞭さは驚きであり、努力の価値があります。
いつものように、音楽を楽しむことを忘れずに。
ヴィンス・ガルボ
参照文献
Dedicated AC power lines and wall power improvements for audio. By Vince Galbo